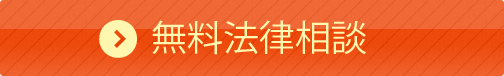自己破産を申し立てると、銀行口座が凍結されます。これは、債務者の財産を保護し、公平な債務整理を行うための重要な措置です。凍結されると、口座からの引き出しや振り込みなどの取引が制限されるため、その間、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、自己破産と銀行口座の凍結について解説いたします。
特に、当法律事務所の相談者,依頼者用のチェックリストとして作成しておりますので、ご確認のうえご対応頂きますようお願い致します。
破産準備を開始する時点での注意点(注意点をチェックしてみてください)
詳細については、法律事務所でのご面談時にご説明をさせて頂きますが、不安やご不明な点がございましたらお問合せください。
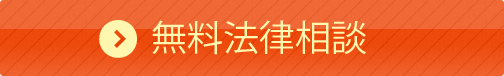
銀行口座が凍結されること
自己破産と銀行口座は密接な関係にあります。自己破産を申し立てると、裁判所からの通知を受けた銀行は、債務者の口座を凍結します。これは、債務者の財産を保全し、公平な債務整理を行うための措置です。
通常、自己破産の申立てが裁判所に受理されると、裁判所から銀行に通知が送られ、口座凍結が開始されます。凍結の対象となるのは、個人名義の普通預金口座や貯蓄預金口座が主です。銀行口座が凍結されると、その時点で残っている残金について「相殺」をされることになります。つまり、債務の弁済に充てられます。
凍結されると、口座からの引き出しや振り込みなどの取引ができなくなります。この口座凍結は、自己破産の手続が完了するまで続き、この間、日常生活に必要な資金の管理が困難になる可能性があります。
そのため、受任通知を発送する前に、事前に銀行口座の残金を確認し、
預金が残っている場合、引き出しをしておく必要があります。
「なけなしのお金を弁護士費用に充当するつもりで、銀行口座に残しておいて、凍結された」ということになった場合、銀行は引き出しに応じてくれないため、破産の計画が大きく変わってしまうという可能性もあります。十分に注意が必要です。
凍結口座へ、後に入金されたお金が引き出せない可能性
受任通知発送時点において、銀行口座には預金残高がなく、銀行口座凍結により相殺されるお金がなかったとしても、
事後的に「凍結された銀行口座」へ未回収の売掛金が振り込まれるというケースがよくあります。
弁護士の受任通知が銀行へ届いた後、凍結された銀行口座へお金が入金されたとしても。
法律上「相殺禁止」といって、後に振り込まれたお金と銀行の貸付金を相殺することは認められません。
ただ、銀行の担当者は、法律の専門家ではないため、相殺禁止であることを理解してもらうことがまず大変です。この理由を理解してもらったとしても、後に振り込まれたお金の引き出しについて、保証をしている保証協会から代位弁済を受ける際に「保証協会の了解をもらわないと銀行では判断がつかないという対応」をされることが多く(保証協会の了解をもらえるケースの方が多いです。)、さらに保証協会の了解をもらったとしても、「破産申立て前に預金の引き出しには応じないという対応」をされることもあります。
未回収の売掛金から、破産費用に充当することを予定していたとしても、銀行に売掛金分を凍結されたままの状態になり、動きが取れなくなるということが起きてしまいます。このような事態を回避するため、弁護士介入時点のタイミングを計算し、未回収の売掛金の支払時期まで時間的な余裕がある場合は、各取引先へ弁護士預り金口座へ振込をしてもらえるよう、請求書を出し直すという対応をすることが考えられます。
また、未回収の売掛金の支払時期が直近になっていて、各売掛先に支払先口座の変更をお願いする時間的な余裕がなければ、弁護士介入時点を遅らせるということも考えられます。
銀行の名寄せにより、他支店口座も凍結される可能性
自己破産を申し立てると、「銀行の名寄せ」により、同じ銀行の他支店の口座も凍結される可能性があります。名寄せとは、預金者が同一の金融機関に複数の口座を持っている場合、その口座残高を合算して預金保険で保護される預金の総額を確定することです。同一人物の情報をデータベースで照合し、同じ銀行内において異なる支店でも一致する情報を関連付けます。
例えば、A銀行の梅田支店から借入れを行い、A銀行の難波支店に別に銀行口座を開設しているような場合、弁護士介入によりA銀行梅田支店の銀行口座が凍結されることは上記記載のとおりですが、それとは別にA銀行難波支店の銀行口座に対しても口座凍結がかかる可能性があります。
理屈でいうと、債権者は同じA銀行になるため、支店が違ったとしても口座凍結を行うことに問題がないということになります。 受任通知は、借入れのあるA銀行梅田支店に発送をすることになりますが、念のためA銀行梅田支店の銀行口座だけでなく、流れとしてA銀行難波支店の銀行口座も凍結の可能性を考えて預金を引き出しておく方がよいでしょう。 現実に、りそな銀行が他支店まで名寄せをして、口座凍結を行うという対応をよく行っています。
銀行口座の引落しが止まらないこと
自己破産の申立てが行われると、裁判所から銀行に通知が届きます。この通知を受け取った銀行は、速やかに口座の凍結手続きを開始します。通常、通知が届いてから数日以内に口座が凍結されます。銀行によって対応の速さに若干の差はありますが、多くの場合、通知を受け取ってから1〜3営業日程度で凍結処理が完了します。ただし、週末や祝日を挟む場合は、さらに時間がかかることもあります。
凍結が完了すると、ATMでの引き出しやインターネットバンキングの利用、口座振替などのすべての取引が停止されます。この時点で、破産者は当該口座を利用できなくなります。
借入れのある銀行の銀行口座で公共料金の支払いを行っていた場合、銀行口座が凍結されると、今後、同口座での公共料金の支払いができなくなります。関西電力、大阪ガス、水道局等へ、連絡を入れて、支払方法の変更手続きを行う必要があります。
借入れのない銀行口座であっても、クレジット等の引落しの可能性があれば、預金を引き出しておく方がよいでしょう。 なお、同じ口座からクレジットの引落しの他、電気、ガス、水道、携帯電話、インターネットプロバイダー、ケーブルテレビ、新聞、NHK等の引落しを行っているような場合、「クレジットの支払いに充てず、公共料金の引落しに充てたい」と考えたとしても、そのような選択ができるわけではありません。意図せず「クレジット分」として引き落とされる可能性があります。 このような場合、銀行口座から預金を引き出し、一旦、全ての支払いができない状態にしたうえで、個別に対応します。電気代であれば関西電力、ガスであれば大阪ガス等、支払方法の変更手続きを行い、請求書を送ってもらって支払うのか、あるいは別の銀行口座からの口座振替手続きをするのかを選択することになります。その際に、支払いができなかった月の分について請求書を送ってもらって支払うようにすればよいでしょう。
一時的な対応として、コンビニエンスストアでの支払いや振込用紙での支払いに切り替えることも一つの方法です。ただし、これらの方法は手数料がかかる可能性があるため、長期的には新しい口座での自動引き落としに戻すことをおすすめします。
公共料金以外にも、携帯電話料金や保険料、家賃など、定期的な引き落としがある場合は同様の手続きが必要です。各サービス提供会社に連絡し、支払い方法の変更について相談・依頼しましょう。
凍結される口座へ、これまでお給料の振り込みをしてもらっていた場合も同様に、給料の支払先銀行口座の変更手続きをお勤め先へ行う必要があります。
なお、自己破産、個人再生を行う準備に入った後であっても、新しく銀行口座を開設することは自由にできます(法人を除く)。これまで取引がない銀行に新規で銀行口座を開設し、その口座で電気・ガス・水道等の引落しを新たに設定することは問題がありません。口座を新しく作る場合にも、まずは弁護士にご質問ください。
銀行口座振替、クレジット決済が今後できなくなること
自己破産を申し立てると、クレジットカードの支払い口座も影響を受けます。通常、クレジットカードの支払いは銀行口座からの引き落としで行われますが、破産手続が開始されると、その口座も凍結される可能性が高くなります。凍結されると、クレジットカードの支払いが滞る可能性があるため、現金での支払を検討するなど、事前に対策を講じる必要があります。
借入れのない銀行口座からクレジットの支払等、引落しで決済をしている場合、弁護士介入後は「引落しをしてはいけない」ということになるはずなのです。しかし、クレジットカードの場合は決済のシステム上、直前のストップができないという扱いになっています。 そのため、借入れのない銀行口座であっても、クレジット等の引落しの可能性があれば、預金を引き出しておく方がよいでしょう。
また、最近多いのが、ポイントがたまるため、「公共料金の支払いをクレジット決済にしている」というケースです。この場合も今後、クレジット決済ができなくなるため、同様に、クレジット決済から、郵便振替やコンビニでの支払いなど他の手段へ支払方法の変更手続きを行う必要があります。
法人、事業主の場合、公租公課(税金等)の差押えの可能性があること
法人名義の銀行口座は、個人の自己破産手続きとは原則として別個に扱われます。法人格を持つ会社の口座は、個人の破産とは独立して存続することが可能です。ただし、個人事業主の場合や、法人と個人の財産が明確に区別されていない状況では、法人口座も調査対象となる可能性があります。
借入れのない銀行口座であり、かつクレジット等の引落しもない銀行口座であったとしても、公租公課(税金等)の滞納があれば、税務署・市役所等から「滞納処分」という形で、ある日突然、銀行預金の差押えが入ることがあります。 通常、銀行預金を差し押さえるためには、裁判をして判決を取らないといけません。そのため、民間の債権者からの差押えが突然入ることはありません(仮差し押さえを除く)。 これに対し、公租公課については、裁判手続きを行うことなく「差押え」を行うことができますので、突然、銀行預金が差し押さえられるという可能性があるのです。このような事態を回避するため、弁護士預り金口座に入金を行うということが考えられます。
また、公租公課の差押えは、銀行預金だけではありません。未回収の売掛金があれば、取引先に通知を発送し、売掛金の差押えを行ったり、機械工具類、自動車、保険の解約金、賃借建物の保証金等、あらゆるものに対し差押えを行うことが可能であるため、注意が必要です。
自己破産による銀行口座の調査範囲とその対策
自己破産の手続きを進める際、銀行口座の調査は避けられません。裁判所は債務者の財産状況を正確に把握するため、広範囲にわたる調査を行います。通常、債務者名義のすべての銀行口座が調査対象となり、過去数年分の入出金履歴も精査されます。
家族名義の口座については、原則として調査対象外ですが、債務者本人が実質的に管理していると判断された場合や、債務者の財産が不当に移転されたと疑われる場合は調査対象となる可能性があります。
自己破産の手続きにおいては、財産の隠匿や散逸を避けることが極めて重要です。事前に口座を解約したり、残高を引き出したりすることは、財産隠しとみなされる可能性があり、免責不許可事由に該当する恐れがあります。そのため、このような行為は絶対に避けるべきです。
弁護士と相談しながら、正直に財産状況を開示し、法律に基づいて認められる範囲内で生活に必要な資金を確保する方法を検討することが重要です。自己破産は債務者の生活再建を目的とした制度であり、誠実な対応が求められます。
自己破産で調査される銀行口座の範囲とは?
自己破産の手続きを開始すると、債務者の財産状況を把握するために、銀行口座の調査が行われます。この調査の範囲は、債務者が保有するすべての銀行口座に及びます。具体的には、普通預金、定期預金、貯蓄預金などの預金口座はもちろん、投資信託や株式などの金融商品に関連する口座も対象となります。
調査は、債務者が申告した口座だけでなく、債権者からの情報や金融機関への照会によって判明した口座にも及びます。また、過去の取引履歴や入出金記録も調査の対象となり、隠し資産がないかどうかも確認されます。
さらに、家族名義の口座や共同名義の口座についても、債務者が実質的に管理していると判断される場合は調査対象となる可能性があります。法人名義の口座であっても、個人事業主や役員としての関与が疑われる場合は調査が及ぶことがあります。
このような広範囲にわたる調査は、債権者の利益を保護し、公平な債務整理を行うために必要不可欠です。債務者は、自己破産の申立前に、すべての銀行口座と財産状況を正確に把握し、誠実に開示することが求められます。
財産調査にかかる時間と影響
自己破産における財産調査は、破産管財人によって行われ、通常数週間から数か月かかります。この調査期間中、破産者の全ての銀行口座が詳細に調べられ、資産状況が明らかにされます。調査の影響は広範囲に及び、預金残高、入出金履歴、口座の種類などが精査されます。
調査結果は破産手続きの進行に大きく影響し、隠し資産が発見された場合は免責不許可となる可能性もあります。また、調査中は口座が凍結されるため、日常生活に支障をきたす恐れがあります。特に給与振込や公共料金の引き落としなど、重要な取引に影響が出る可能性があります。
財産調査の範囲は広く、過去の取引履歴も対象となるため、破産申立前の不自然な資金移動なども厳しくチェックされます。このため、破産を検討する際は早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
破産手続における銀行口座の開示義務
自己破産の手続きにおいて、債務者には銀行口座の開示義務があります。これは、破産管財人や裁判所が債務者の財産状況を正確に把握し、公平な破産手続きを進めるために不可欠な要素です。
開示義務の対象となるのは、債務者名義のすべての銀行口座です。普通預金、定期預金、貯蓄預金など、口座の種類を問わず、債務者が保有するすべての口座情報を提出する必要があります。また、個人名義だけでなく、事業用の口座や共同名義の口座も含まれます。
開示する情報には、口座番号、口座名義、銀行名、支店名、口座の種類、残高など詳細に渡り、これらの情報は、破産申立書類の一部として提出されます。虚偽の申告や情報の隠蔽は法律違反となり、破産免責が認められない可能性もあるため、正直に申告することが重要です。
管財事件に発展する場合の注意点
自己破産の申立てが管財事件に発展した場合、銀行口座の扱いにはより慎重な対応が求められます。管財人が選任されると、債務者の全財産が管理下に置かれるため、銀行口座の調査範囲も広がります。この場合、複数の金融機関にある口座も含めて、より詳細な財産調査が行われることになります。
管財事件では、債務者は自身の全ての財産を正確に申告する義務があります。隠し口座や未申告の預金が発覚すると、免責不許可となる可能性が高まります。また、管財人は債務者の収入や支出を厳密に管理するため、生活費の使用にも制限がかかる場合があります。
さらに、管財事件では破産手続きの終結までに時間がかかるため、口座凍結の期間も長期化する傾向にあります。この間、日常生活に必要な資金の管理方法について、管財人と綿密に相談する必要があります。場合によっては、管財人の管理下で使用できる特別な口座が設けられることもあります。
管財事件に発展した際は、弁護士や管財人の指示のもと、全ての財産を正直に開示することが重要です。
銀行口座の凍結が解除される条件
自己破産による銀行口座の凍結が解除される条件は、通常、破産手続きの終了を待つ必要があります。裁判所から免責許可決定が出されると、破産管財人が債権者への配当手続きを完了し、破産手続きが終結します。この時点で、銀行に対して凍結解除の通知が行われ、口座の利用が再開できるようになります。
凍結解除までの期間は、破産手続きの複雑さや債権者の数によって異なりますが、一般的に数ヶ月から半年程度かかることが多いです。
まとめ
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がありますが、借り入れをした借金が、どうしても返済できない場合、任意整理など他の債務整理での解決が難しい事例での対処法として検討されるのが「自己破産」です。
自己破産を申し立てると、銀行口座が凍結されます。これは、債務者の財産を保全し、公平な債務整理を進めるために必要な措置です。口座が凍結されると、口座の資金に対する引き出しや振り込みが制限され、日常生活への影響が出ることがあります。特に、未回収の売掛金が入金された場合でも、これらの資金は引き出すことができなくなる可能性があります。
自己破産の申立てがあると、銀行は裁判所からの通知に基づいて口座を凍結します。この凍結は自己破産手続きが完了するまで続くことが多いので、その間は日常生活に必要な資金の管理が困難になり得ます。このため、弁護士との相談を通じて、自己破産手続きの各段階で適切な対応を計画することが望ましいです。
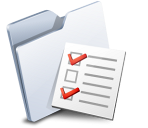
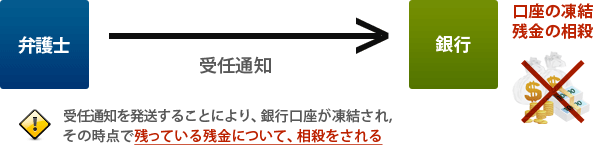



 メールで相談
メールで相談 メールで相談
メールで相談